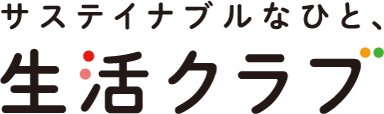第7次エネルギー基本計画案にパブリックコメントを提出しました
第7次エネルギー基本計画(案)に対する意見
2025年1月23日
生活クラブ生活協同組合・愛知
理事長 中野京子
<はじめに>
生活クラブ生活協同組合は、脱原発・脱炭素、そして再生可能エネルギー100%の社会を実現すことで、気候危機への解決に向けて自然と人が共生する持続可能な社会づくりを目指しています。
地球温暖化による気候変動で、日本でも毎年のように気候災害が発生しています。産業革命以前と比べ世界の気温上昇を1.5度に抑えるには、二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスを世界全体で2035年には2019年比で60%削減が必要です。政府案は2013年比で60%削減とし、これを世界標準の2019年比にすると53%という低さです。これまで大量の温室効果ガスを排出してきた先進国として、気候変動対策をリードするためにも、2013年比ならば2035年には75~80%削減を目標にするべきです。
そこで、私たち生活クラブ生協は、➀民主的で透明性のある議論。➁原子力発電の廃止。➂火力発電の廃止。④省エネルギー・再生可能エネルギーの推進。の4点について、以下の通り提案します。
<民主的で透明性のある審議を>
あらゆる国民が影響を受けるエネルギーの在り方、気候変動対策を決定する場にも関わらず、そのプロセスに市民が参加する機会がほとんどありません。
審議会の構成メンバーの年齢や性別の偏りをなくし、特に今後影響を受ける若い世代、多様な立場の専門家、環境団体が多数参加できるようにするべきです。
また、エネルギー政策は内容が専門的で複雑です。審議される論点や議論内容を分かりやすく、時間をかけ、もっと民主的かつ透明性の高い議論が必要です。
<原子力発電の廃止>
第6次エネ基に記載された「可能な限り原発依存を低減する」の文言をなくし、「原発を最大限活用する」としたことは問題です。
能登半島地震で北陸電力志賀原発に予想していなかった事故が次々と生じたように、 地震・火山国の日本で原発を稼働させることは極めて危険です。さらに、ロシアによるウクライナの原発が軍事標的にされた例もあります。これ以上、将来世代に負の遺産を押し付けることはやめるべきです。
また、数兆円のコストをかけて新増設やリプレースしても出来上がるまで数十年かかり、気候変動対策としては意味がありません。
<火力発電の廃止>
地球温暖化対策に逆行する化石燃料を使った火力発電を今後も温存し、G7の中で唯一、石炭火力発電の廃止期限を明らかにしないことは重大です。
また、技術的に実現の目途が立っていない CCS や水素やアンモニア専焼発電を前提とした計画は意味がありません。高効率とする石炭火力もその CO2 排出量は「非効率」なものと大差なく、天然ガス火力の2倍以上です。
化石燃料を毎年数十兆円かけて輸入するのではなく、省エネや再エネに投資することでエネルギー自給率を高めてください。
<省エネルギー、再生可能エネルギーの推進>
第6次エネ基に記載された、再エネの「最優先の原則」を削除したことは問題です。再エネは最優先でかかげ、2040年までに電力構成の100%に近づける方向性を示すべきです。
省エネを進めるために、建物の断熱基準を強化してください。再エネの導入を加速化するための制度や政策、仕組みづくり、社会的合意形成などを計画の優先としてください。
再エネの発電コストは下がり続けています。全国のあらゆる地域に広げることで温暖化防止に貢献でき、エネルギー自給率を高めることができます。
生活クラブ生活協同組合は、脱原発・脱炭素、そして再生可能エネルギー100%の社会を実現すことで、気候危機への解決に向けて自然と人が共生する持続可能な社会づくりを目指しています。
地球温暖化による気候変動で、日本でも毎年のように気候災害が発生しています。産業革命以前と比べ世界の気温上昇を1.5度に抑えるには、二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスを世界全体で2035年には2019年比で60%削減が必要です。政府案は2013年比で60%削減とし、これを世界標準の2019年比にすると53%という低さです。これまで大量の温室効果ガスを排出してきた先進国として、気候変動対策をリードするためにも、2013年比ならば2035年には75~80%削減を目標にするべきです。
そこで、私たち生活クラブ生協は、➀民主的で透明性のある議論。➁原子力発電の廃止。➂火力発電の廃止。④省エネルギー・再生可能エネルギーの推進。の4点について、以下の通り提案します。
<民主的で透明性のある審議を>
あらゆる国民が影響を受けるエネルギーの在り方、気候変動対策を決定する場にも関わらず、そのプロセスに市民が参加する機会がほとんどありません。
審議会の構成メンバーの年齢や性別の偏りをなくし、特に今後影響を受ける若い世代、多様な立場の専門家、環境団体が多数参加できるようにするべきです。
また、エネルギー政策は内容が専門的で複雑です。審議される論点や議論内容を分かりやすく、時間をかけ、もっと民主的かつ透明性の高い議論が必要です。
<原子力発電の廃止>
第6次エネ基に記載された「可能な限り原発依存を低減する」の文言をなくし、「原発を最大限活用する」としたことは問題です。
能登半島地震で北陸電力志賀原発に予想していなかった事故が次々と生じたように、 地震・火山国の日本で原発を稼働させることは極めて危険です。さらに、ロシアによるウクライナの原発が軍事標的にされた例もあります。これ以上、将来世代に負の遺産を押し付けることはやめるべきです。
また、数兆円のコストをかけて新増設やリプレースしても出来上がるまで数十年かかり、気候変動対策としては意味がありません。
<火力発電の廃止>
地球温暖化対策に逆行する化石燃料を使った火力発電を今後も温存し、G7の中で唯一、石炭火力発電の廃止期限を明らかにしないことは重大です。
また、技術的に実現の目途が立っていない CCS や水素やアンモニア専焼発電を前提とした計画は意味がありません。高効率とする石炭火力もその CO2 排出量は「非効率」なものと大差なく、天然ガス火力の2倍以上です。
化石燃料を毎年数十兆円かけて輸入するのではなく、省エネや再エネに投資することでエネルギー自給率を高めてください。
<省エネルギー、再生可能エネルギーの推進>
第6次エネ基に記載された、再エネの「最優先の原則」を削除したことは問題です。再エネは最優先でかかげ、2040年までに電力構成の100%に近づける方向性を示すべきです。
省エネを進めるために、建物の断熱基準を強化してください。再エネの導入を加速化するための制度や政策、仕組みづくり、社会的合意形成などを計画の優先としてください。
再エネの発電コストは下がり続けています。全国のあらゆる地域に広げることで温暖化防止に貢献でき、エネルギー自給率を高めることができます。